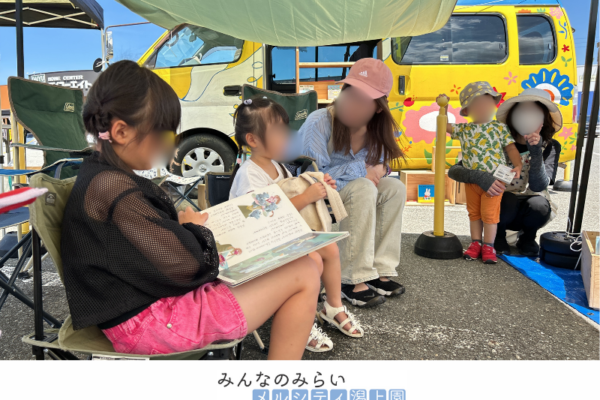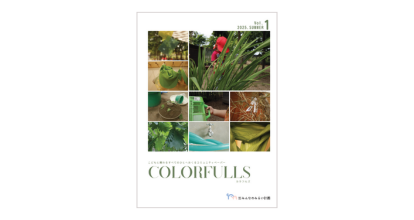
無農薬米の社内自給率を上げるため、今年から星山えほんの森保育園 菜園担当のガッツさんの田んぼも無農薬に取り組んだ。無農薬米を栽培するためには、あらかじめガジという櫛のようなもので30センチ幅の線を格子状にひき、線が交差した場所に4,5本ずつ手で苗を植えていく。そして、その幅に合わせた手押しの除草機で何度も除草作業に入る必要がある。昔は親戚や地域で集まってみんなの田んぼを順番に植えていたが、機械化が進み、米どころの岩手であっても生産者と消費者の分離が進んでいる。しかし、いつも給食でお世話になっている協力農家さんたちは、人の手がたくさん必要となる田植えを”選んで”行っている。それはある種の祭りであり、昔ながらの「お互い様」精神が残っている。

【写真=田植えの合間のこびり(=おやつ)やお昼がうれしい。】
今回、星山・ガッツさん・東和のウレシパモシリさん・同じく東和の古松自然農園さんの田植えにお邪魔したが、農家さんと共に田植えをしていると、(当然ながら)ただ植えればいいわけではないことに気が付く。黒い土、赤っぽい粘土、ラクダ色の土、とろとろ、ねっとり、水が抜けやすい、溜まりやすい、傾斜、土の溜まりやすい場所のあるなしなど、田んぼは田んぼでも特徴は様々。農家さんはその田んぼに合わせて調節しながら田植えをしていく。
【写真=古松さんの棚田のため池】
【写真=山にそって作られた棚田】
古松自然農園さんの田んぼは用水路がない。棚田の一番上にため池があり、そこから水を引いて下の田んぼにまわしている。それは星山の子どもたちが、水場から割った竹に水を流し、下のバケツに水をためている姿を彷彿とさせる。規模感は全く異なるものの自然の原理を体験として理解し、傾斜をつけたりせき止めたりして何度も実験を繰り返し、目的の場所に水を流す。子どもたちの遊びは延長線上に暮らしがあり学びがあるのだとはっとした。昔の農村部の子どもたちは農業を手伝いながらそうやって当然のようにからだで学んでいたのだろう。便利になるだけでは学べないことが、昔ながらの農業にはつまっている。本物の学びがすぐそばにあるこの環境に感謝したい。
【写真=子どもたちが水場から桶まで竹をつかって水を流しいれる様子】